
|
トップページ > 宅建免許コラム
|
平成30年8月1日
テーマ 宅建業新規
前回に続き、当事務所に実際にご依頼があった、もしくはご相談があったケースで宅建免許を申請できなかった、もしくは他の方法を取らざるを得なかったケースをご紹介します。
|
複数の会社を経営している場合に多いのですが、登記上は別々の会社であっても、実際には事務所の所在地、従業員などはすべて同じである場合があります。
宅建免許の取得には、専用の独立した事務所が必要になるため、事務所が他の会社と共同では、免許の取得条件を満たすことができません。
固定式のパーテーション等を使って完全に部屋を区切ってしまうことにより事務所として使用することもできますが、大がかりな工事が必要になるため、あまり現実的ではありません。
実際には、新しく別の事務所を準備して頂くか、既存の会社で免許を取得して頂くしかなくなってしまいます。
また、事務所としては独立した別の部屋であっても、その事務所にたどり着くまでに他の会社を通過しないと行けない場合にも、同様に事務所としは使用できません。
|
|
法人の場合は社会保険への加入が義務づけられていますが、実際には、まだまだ未加入の会社も多く存在します。
宅建免許の取得には、今のところ社会保険の加入が条件とはなっておりませんので、未加入であっても免許を取得するはできます。
ただし、宅地建物取引士、代表者等の常勤を証明する書類として取得する会社名の入った健康保険証の添付が必要になります。
当然のことながら社会保険未加入の会社は、健康保険証を添付することができませんので、他の書類で代用することになりますが、その中の1つに前の職場の退職時の源泉徴収票が必要になる場合があります。
源泉徴収票自体は発行の義務がありますので、本来なら受け取っているはずですが、アルバイトであったり、しっかりとした職場でなかったりすると作成していなかったりする場合もありますし、発行されていても紛失してしまっている場合もあります。
こういった状況でも、免許を取得するためには前の職場にお願いして源泉徴収票を発行してもらわなければなりません。前の職場を円満に退職していないと、頼みづらかったり、発行してもらえなかったりしますが、こういった事情は役所は考慮してくれません。
書類が取得できないと、きっちりと社会保険に加入してもらうしかなくなってしまいます。
|
|
宅建免許を新規で申請する場合には、まず他の会社で専任の宅地建物取引士になっていないか、他の許認可で専任が必要な職に就いていないかを確認され、他社で登録されている場合には、申請自体を受理してもらえません。
前の職場で専任の取引士登録をされていて、まだそのままになっている場合には、たとえ退職した実態があったとしても、前の会社が外す手続きをするまでは申請ができないことになっています。
前の職場がただ手続きを忘れているだけであれば、お願いしてすぐに手続きをしてもらえばなんとかなりますが、後任の宅地建物取引士が決まっておらず、外したくても外せない場合には、困ったことになります。
こういった事情を役所に訴えたとしても、変更手続き自体は30日以内に申請すればよいことになっていたりして、役所がなんとかしてくれることはまずありません。
退職しても同じ不動産業であれば何らかの形でかかわってくることもありますので、事前に退職を伝え、いつまでに外してもらえるか確認をしておくなど、できる限り、円満に退職されて下さい。
|
|
サラリーマンの方が副業として不動産業を始めたいというご相談でした。
本人が代表者兼宅地建物取引士としての開業を予定しておりましたが、他の会社で勤務しているわけですので、当然のことながら常勤にはなりません。
ご本人としては、休日しか営業しないので、営業中は常に常勤しているというお考えでしたが、役所はそういった個別の事情は考慮してもらえません。
代わりに誰かを雇用すれば免許の取得は可能ですが、副業としてはあまり現実的ではありませんので、断念せざるを得ませんでした。 |
上記のケースはあくまで愛知県での場合です。他県では認められたり、認められなかったりする場合があります。
また、審査基準の変更などもあります。
|
|
|
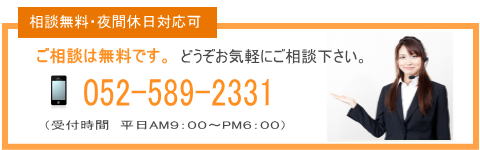 |
|


